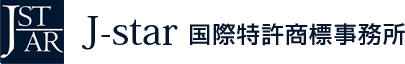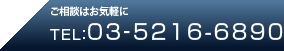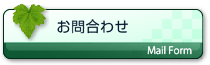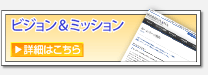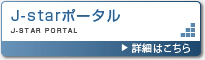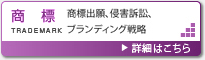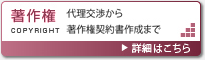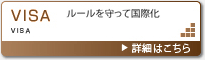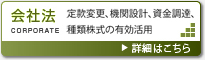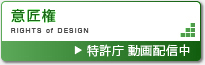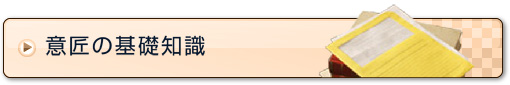
CHAPTER-1
1・意匠法上の意匠とは?
意匠法上の意匠は、物品のデザインであると言えます。物品のデザインであれば、原則として、意匠法上の意匠となり、保護の対象となります。
例えば、ハンカチーフで作成したモチーフや、HPの画面デザインなどは、物品に施されたデザインとは言えないため、現在では、意匠法上の意匠として保護されておりません。
主に、工業デザイン(バイク、携帯電話等)などが、保護対象とイメージするとわかりやすいと思います。
CHAPTER-2
2・意匠権取得のメリット
他社の模倣を排除
意匠権を取得したデザインと同一又は類似範囲のデザインに独占排他権を取得出来
ます。よって、他社の模倣品に対しては、差止請求、損害賠償等の権利行使を通
して、排除することが可能となり、存続期間中(登録から20年)独占してデザイン
を使用出来ます。
商品のブランド戦略
購買意欲を発揮するデザインは、デザインそれ自体で商品のブランド力向上に寄与
します。また、意匠登録番号を商品に付すことにより、商品の信頼性をアピール
出来ます。
特許権などの技術的な権利の補完的役割
特許権などによる権利化は出来なくても、意匠権を取得することにより、デザイン面
からの保護が可能となります。 更に、意匠権は、外観からその権利範囲がわかりや
すく、同じ模倣品が出た場合に、特許権による権利行使に比べて、その費用や時間が
少なくて済むメリットがあります。特に、最近では、技術力はないが、デザインは
模倣出来る能力を有する途上国での、知的財産戦略において、有効と思われます。
CHAPTER-3
3・意匠登録出来ないケースは?
①量産出来ない、一品制作物などは、意匠法では保護されません。
(著作権法では保護されます。)
②今までにない斬新なデザインでない意匠は、保護されません。
③意匠の販売や市場調査などで、相当期間経過後(6ヶ月以上)に出願する場合は、
新規性が喪失しているので、意匠登録出来ません。
(登録出来ても、権利行使が制限されます。)
④簡単に創作出来そうな意匠も、保護されません。
⑤公益上適切な意匠でないと保護されません。
例えば、模様として、他人の著名な商標等を取入れている場合などです。
CHAPTER-4
4・意匠登録手続きのフロー
下記は意匠権を取るまでの手続きフロー図です。
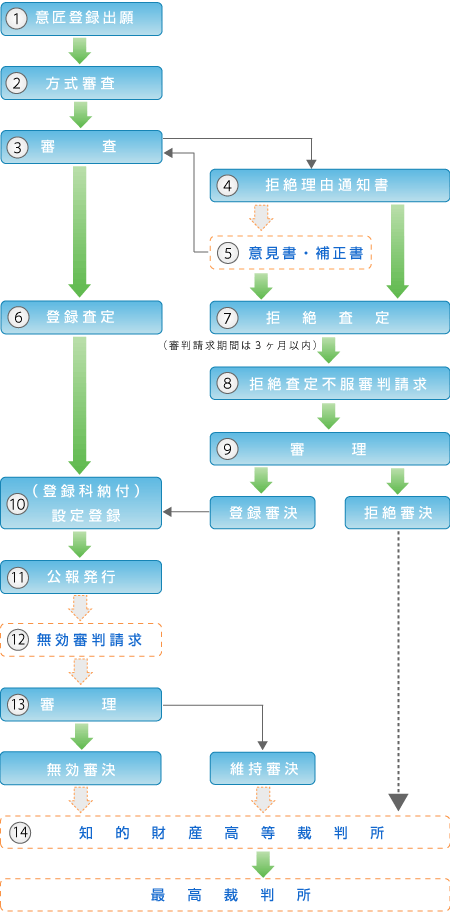
CHAPTER-5
5・意匠権の維持
意匠権は、意匠権の設定登録から最大20年間存続します。
取得した意匠権を維持するかどうかは、意匠権取得の目的や、ビジネス上の
利用可能性を判断する必要があります。
維持する場合には、毎年、維持登録料を特許庁に支払います。
例・・・・
第1年から第3年まで・・・・毎年8,500円
第4年から第10年まで・・・毎年16,900円
第11年から第20年まで・・毎年33,800円